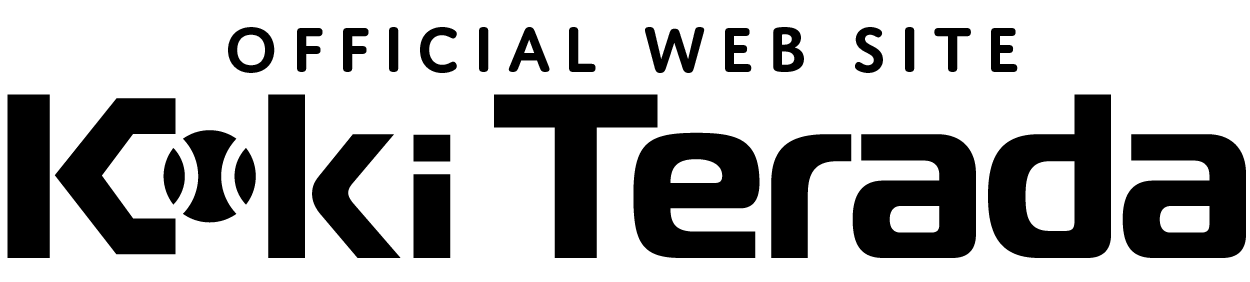何かを成し遂げた時、それは決して一人だけの力ではない。そしてそれは綺麗事だけで終わる話でもないということ。これまで他人に語ることはなかった苦悩、葛藤、強さ、その生き様に込められた想いを、少しでも多くの方に見ていただきたい。今回は前編に引き続き元DeNA・山本武白志が語る野球への想いを綴っていく。(前編はこちらから)
中学生離れしたメンタリティ
『制服とか私服のときに汗をかくのが大っ嫌いなんですよね。だから学校の休み時間は教室で友達と雑談とかしてましたよ。』
そんな武白志だが、ユニフォームを着ると話は変わるのだ。小学生時代からの勢いそのままといったところだろうか。中学生になった武白志は神奈川県内のチームで硬式野球を始め、大会での成績は抜群であった。2年生の時に臨んだ大会では、準決勝までに8打数7安打8打点、決勝では完投しチームを優勝に導いた。『MVPに選ばれると思ったんですけど、獲得したのは1番バッターの選手でしたね。』と、冗談めかして話してくれたが、その才能はやはり放っておかれなかった。武白志は報知新聞にとりあげられることになり、なお一層の注目を集めるようになった。ヤンチャ盛りの中学生であれば普通は浮かれてしまいそうなものだが、武白志は淡々と言い切った。
『もちろん嬉しいとは思っていましたけど、浮かれるという事はなかったですね。いわゆる「調子に乗ってしまう」という事は、予想以上のことが起きているからだと思うんです。僕は有名になって当たり前、注目されて当たり前だと思ってやってきたので。さらに高みを目指すだけですよ。』
はたしてこれが中学生のメンタリティなのだろうか。理想の自分を常にイメージし、それを実現させることはもはや既定路線だと確信しているからこその立ち振る舞い。大人でもなかなか難しいことだと感じながら、話題は進路のことへと進んでいった。
当然、これほどの逸材を欲しがる高校は多かったことだろう。しかし、意外にも武白志本人が自覚していた誘いの話は、横浜高校と九州国際大学附属高校(以下九国)の2校からのみだった。そして後に九国に進学するのだが、地元の強豪校ではなくあえて県外に出た理由を教えてくれた。
『横浜高校って、やっぱハマっ子の憧れじゃないですか。だからかなり気持ちは揺らぎましたよ。ただ、僕がマッチしそうだなって感じたのは九国でした。選抜で準優勝した時のチームが打ちまくってたイメージがあったんで、最終的には九国を選びました。』
憧れを捨てて、自分が輝けるであろう場所を合理的に選んだ彼は、その選択を正解にしていくのであった。

甲子園での屈辱
甲子園に2年連続出場、3年時には2打席連続ホームラン、秋にはドラフト指名。中学までの話や高校での出来事だけを見ると、才能に恵まれた野球エリートが既定路線を走っているんだなと、そう感じる方も少なくないだろう。正直にいうならば、まさに武白志は既定路線を突っ走っていたと私は感じている。ただその路線は、程よく整備された綺麗なものでもなければ加速装置付きの乗り物に乗って進めるようなものでもないのである。山頂に近づくにつれて悪化する天候に見舞われながらも気力で登りきり、そこで見た土砂降りの景色を『綺麗だ』と言い切るしかなかった、そんな山登りのような路線ではないだろうか。
ピンとこない例えは置いておいて、武白志は2年生の夏、地方大会で2本塁打12打点の成績を引っ提げて甲子園に乗り込む。ここまでは順調な路線を進んでいた武白志だったが、甲子園という舞台はそこまで甘くなかった。一回戦、4打数0安打3三振。チームも初戦敗退となった。かつてない不振に喘いだ武白志は当時の心境を聴かせてくれた。
『甲子園が決まって、やっと全国ネットで試合が放送されるから「みせてやろう」って思ってましたね。ただこの結果で、ショックとは少し違うけどめちゃくちゃ悔しかったです。イメージとは真反対の結果で、このままじゃ終われない、甲子園で受けた屈辱は甲子園でしか返せないって思ってましたね。』
この屈辱が、武白志を奮い立たせたのはいうまでもない。甲子園に出られて満足ではないのだ。再びあの場所に立つ日まで、全力で駆け抜ける。ただひたすらに練習に打ちこんだ。気がつけば秋を迎えていた。しかし、その季節に待ち受けていた現実は、高校生が受け止めるには厳しすぎるものであった。